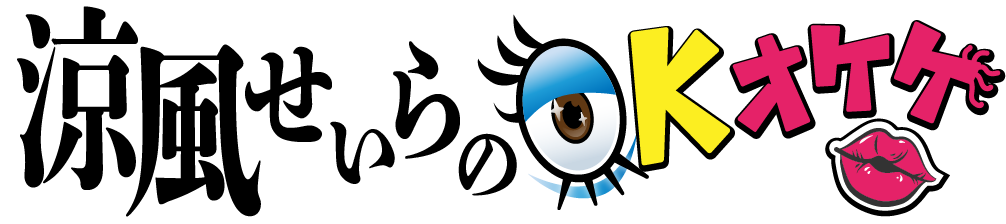力なく電話を切った才蔵の目に通路奥のトイレのドアが開き、清々しい表情の涼風の姿が見えた。真っ赤な巾着袋を大切そうに胸に抱えながら「あースッキリしたー」と破顔している涼風だ。

くそ…。あん袋ん中に違法薬物があるとに、なして見逃しきるちゅうばい、お父しゃんは年ばとり精神が弱うなってきてあげんことば言うたが、俺はあん頃から正義ば貫いて生きてきたんや、それば今になって目ん前のズルに瞳ば閉じるわけにはいかんのや…。
才蔵が涼風の真っ赤な巾着袋を睨み見ていると涼風が近づきながら話しかけてきた。
「才蔵、そこでそんな怖い顔をして、なにをしてるの? あ、わかった〜トイレを待ってたのね、今は誰も入ってないわよ、OKオケケよ」

「…」。
才蔵は真っ赤な巾着袋を見ていた。
「あ、そうだ〜思い出した、あんたさ〜今朝の電話、あれ失礼よ〜私が一生懸命に話をしてるのに途中でクゥークゥーって(!)ギャッ!ちょっとなにをするのよ!」

涼風は慌てた。
才蔵が真っ赤な巾着袋を奪いとったのだ。
「返しなさいよ」。涼風が金切り声をあげた。
「あなたは…あなたは…」。才蔵の息があがる。
「返しなさいって言ってるでしょー」
涼風の怒鳴り声を聞きつけて楽屋にいた役者たちがゾロゾロと廊下に飛び出してきた。なんだ? どうした? 「博多通りもん」を食べながらオカダ三太は隣にいた三四郎に不思議そうに聞いた。

アロハ・オギクボは通路の光景を見つめながら唇を噛んだ。
あの人、なにをやってくれたんだよ…この舞台どうなっちゃうんだよ、本番まで三十分を切ってんだぞ。
令和2年6月25日