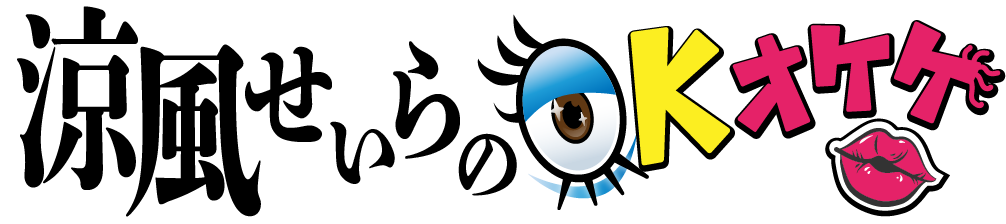それからの一時間ほどの会話はたいした盛りあがりもなく、話題は軍隊経験をしたミンソンの話へと移り、おおー凄いなーとなり、ジホはいつ行くの?そんな細い体で大丈夫なん?
鉄砲とか持って走れるの?筋肉は大事だよ。泣いちゃうんじゃないのーなどと、いじられていたジホだったが口を真一文字にして「ボクだってガンバリますよ、国のために」、と言ったひと言に、そうだよな、考えれば韓国って休戦中なんだよな、「つまりは戦争中なんだよね」、と多少のかじりついた程度の知識を引っ張りだしながらアーヤンと栄次は徴兵制度の韓国はすごいなーと結んだ。

さあそろそろ散会だとなり、ジホが勘定伝票を見ながら携帯の電卓で割り勘料金を叩き出したときに、ガッキーが「ごめんね」と呟いた。ン? となった一同が彼を見るとガッキーは申し訳ない顔をしながら、「たいした情報もないのに、みんなに期待させちゃったみたいで本当にごめん」、と頭を下げた。
「もうええよ、そのことは」。アーヤンが笑った。
「涼風さんが押さえてるチケットの人の名前、女の人としかわからなくて…こんな程度の情報で調子にのってた自分が恥ずかしいよ」
「…」。
全員がガッキーを見つめた。
見つめられたガッキーは「え? なに?」、と動揺した。
「女?」「涼風さんにオンナ?」「え、あの人にそういう相手がいたってこと?」「筋肉うずくんだけどー」、凄まじい質問が飛び交うなか、ミンソンが手をあげた。
「ハイ。あと一時間くらい、飲みませんか?」

その頃、六本木の小さなバーで涼風はランランと三四郎とグラスを傾けていた。

「涼風さん、誰なんですか、その奈緒美さんという人?」、とランランが聞いた。
「その人とはどういう関係だったんですか?」
三四郎が涼風の顔を窺いながら尋ねた。
涼風はあの頃を思い出すようにグラスを見つめながら優しく呟いた。
「奈緒美さんは、とっても大切な人なの…」
令和2年7月2日