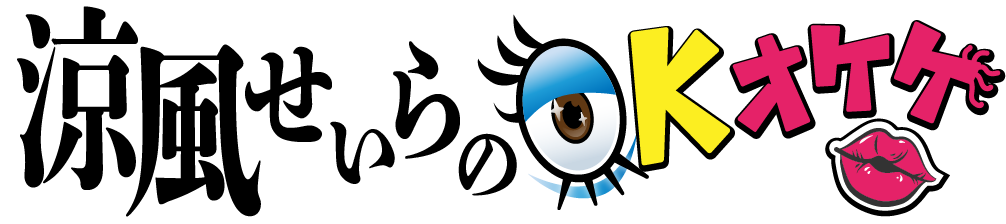深夜のビル警備のバイトはちょろかった。
大手町にある某企業のビルは深夜になっても無人となることはなく、多くの社員たちが残業をしていた。一九八六年、時代は昨年からはじまったバブルという景気の波に乗り、人々は仕事に遊びに多忙を極めている。このビルからひと気が消えていくのは朝方の四時を過ぎた頃である。
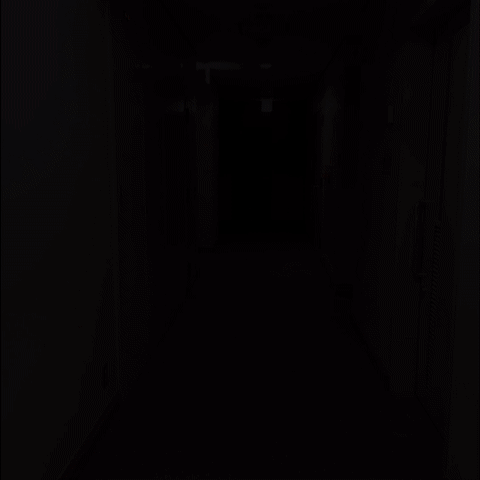
尚太郎は決められた時間になると懐中電灯を片手にビルの廊下や各階のフロアーやトイレ、給湯室の見回りに出かけた。
やることはなにもない。給湯室の窓が開いていたら施錠をする程度だ。すれ違う社員に軽く一礼をして、次にフロアーに顔を出し、異常はありませんか?と問いかけ、そこにいる誰かが、大丈夫でーす、と抑揚のない声で言葉を返す。そのときに再び軽く頭を下げてフロアーを出て廊下を歩く、そして階段を上って次のフロアーを歩く、その繰り返しをするだけで体力も気も使わない仕事だ。このバイトを選んだ理由は夜の警備ということで時給が良いことと、その時間帯にはアパートに居たくないからだった。
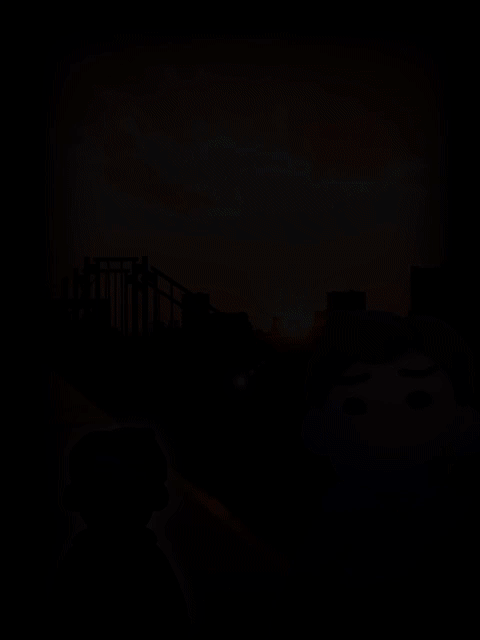
バイトの終わり時間が近づくと、ビルの屋上に出てうっすらと顔を覗きはじめる朝焼けを見つめるのが好きだった。夜と朝の狭間の空には今夜の終わりを告げる星たちが見え隠れしていた。フワリと頬にあたった風は生あたたかく初夏の到来を感じさせてくれた。
「あと二時間で交代か…」、と尚太郎は呟いた。
帰りたくないな、あんなアパートに…。
尚太郎の気持ちは腐っていた。
原因はわかっている。あいつらだ、浩輔と慎一だ。
令和2年7月5日