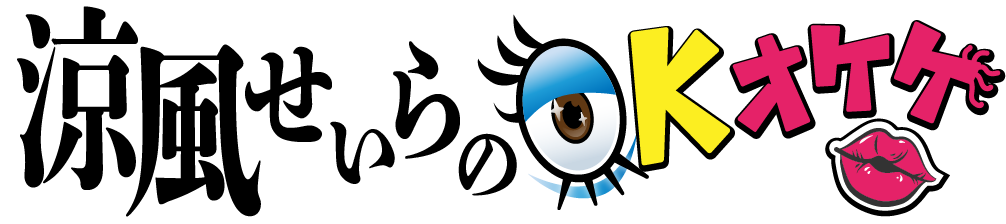14.九字護身法
会計伝票を受け取りにきたアルバイトの女性店員は困惑していた。会計をしてくれというから、このテーブルにやってきたのに一人の客が「ダメダメ、もう一杯だけ飲ませて、ね、ね」と両手を合わせて拝みだしたのだ。飲み屋でよく見る光景だ。帰ろうとしてる同卓の客たちが、その男をなだめている。
「ガッキー、明日も本番があるんやからー今日はここまで、わかった?ハイおしまい、オーシーマイ」
本番という言葉を聞いた店員は、この客たちは舞台役者だと察した。
ったく、お気楽な男たちだと思いながら男たちの顔を眺めると、おおおーオイオイ、イケメンが揃ってるじゃん、と興奮した。
「ね、もう一杯だけ、飲ませて、ね」
「だーめ。ガッキー帰るよ。お姉さん、お会計してください」
「はーい」。女性店員は好みの顔の男に話しかけられたことで舞いあがった返事をした。いそいそとレジに向かう顔が紅潮しているのがわかった。
やべっ、好みだよ好み、私の好物のお顔だー。舞台、どこでやってるのかな?観たいな〜あの人のお芝居。この街で飲んでるということは俳優座かな?明日観に行っちゃおうかな〜と心が弾んだ。ン?え?つまり、あの酔っ払い、ガッキーって呼ばれてたあいつも役者なの?いやいやガッキーは裏方だな、裏方って顔をしてたよ。そんなことを考えながらレジを打ち出した。
役者のガッキーは、この夜、気持ちのいい酒を飲んだ。ここにいるメンバーが自分の存在を、自分の話を必要としてくれたのだ。情報屋として、これほど嬉しいことはない。
「だよねーみんなは俺の情報を知りたいよねーだよねーだって俺はガッキーだよ、情報屋のガッキーだよー」
六本木交差点は地下鉄を目指す人で溢れていた。
「もう一軒行こうーよー」

ガッキーの誘い声虚しく、アーヤンたちは地下鉄日比谷線六本木駅へと消えていった。ガッキーが使う電車は千代田線で、ひとり取り残された格好となった。チッと腐る気持ちで乃木坂駅へと歩き出したとき、向こうから歩いてきたアロハと才蔵がガッキーに気づき、嬉しそうに手を振ってきた。

三人は立ち話をした。
「才蔵くんとアロハの二人飲みなの?え?なになに?才蔵くんとアロハって、そんなに仲良しだったの?」
「ガッキー。聞いてよーねー聞いてー」才蔵は相当に酔っている。
「オレ、今日さ、涼風さんを追いこんじゃったじゃん、シャブと思ったらボラギノールのやつ」
「うん、四個はダメなやつね」
「あれ、ネタ元こいつだから」、才蔵はアロハの首に腕を回しながら「こいつ、オレにガセネタ掴ませて、そんでオレがその気になっちゃってさー」
「だから謝ったじゃないですか。そんで今夜、お詫びの気持ちで奢ったじゃないですかー」
「奢った?オイ、生ビール一杯だろが。あとは、なんでオレが払ってんだよー」
「そこは年上ですもん」
「このやろー本当におまえは可愛いなーこのやろーアーハハハ」。道の往来でじゃれ合いながら笑い合う才蔵とアロハにガッキーは言った。
「ね、もう一軒行かない?」
「は?行かないですよ、明日本番なんですよー無理ですよーガッキーさんの肝臓、どんだけ酒を欲しがってんですかー(笑)」アハハハと笑っていたアロハの目が「!」となった。
「見てください、あそこ」
長い腕を伸ばしたアロハの指先。六本木通りを挟んだ向かい側の道で涼風とアクア九条が言い合いをしている姿が見える。

アロハは生唾を飲みこみながら唸るように呟いた。
「六本木のど真ん中でオカマが喧嘩してます」
「バカ。そういうことを言うな、ウチの幹部だぞ」、才蔵がアロハの頭をコツンとやったそのときだった。ガッキーが車道へと走り出したのだ。我が身の危険を顧みず、行き交う車の隙間を抜けて反対側の歩道へと走っている。
情報屋ガッキーの動きを見ていた才蔵とアロハは呟いた。
「すげえな…忍者みたいだな」
「そうすか?オレには噂好きの団地のおじちゃんにしか見えないんですけど」

「アロハさ、おまえってそんなヤツだったの?人の悪口は言わないと思ってたよ」
「あ〜。スミマセン、猫かぶってました(笑)。今日のボラ事件で才蔵さんとこうなったことで、なんつーかすげぇラクになりました」
「それならそれで良いや。人間、ストレスが一番の天敵だからな、ラクに生きろ、ハハハ」
「それにしても、あの二人、なにを言い争いしてるんですかね?やっぱ今日の帰りがけに揉めてたチケットのことなんですかね?」
「だろうな」
「あれ?気にならないんですか?」
「ま、気にならないことはないけど、気にしちゃうと、オレ、変な方向に頑張っちゃうだろ…。だから気にしないようにするよ」
「本当ですか〜」。アロハが悪い笑顔を見せる。
「本当に我慢できるんですか〜才蔵デカさん」
「よ、よしてくれよ、その呼び方は。お父しゃんのDNAが疼くんだよ」
「疼きましょーガンガンと疼きましょうーよ」。アロハが囁く。
「ダメだって、あ〜疼くばい〜ダメだってば〜」。
才蔵の正義が疼きだす。
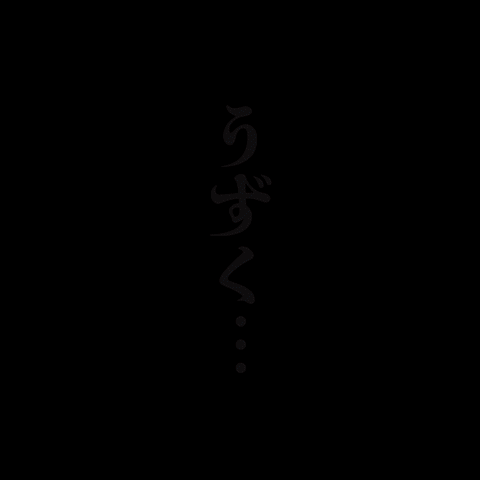
そして、才蔵の目がキランと光ってしまった。
「おお〜キタキタキタァー」。興奮のアロハが叫ぶ。
「う、疼かせるなよー」
「くるよくるよ、きちゃうよー才蔵デカがー」
「じゃあーいっちゃいますかー」
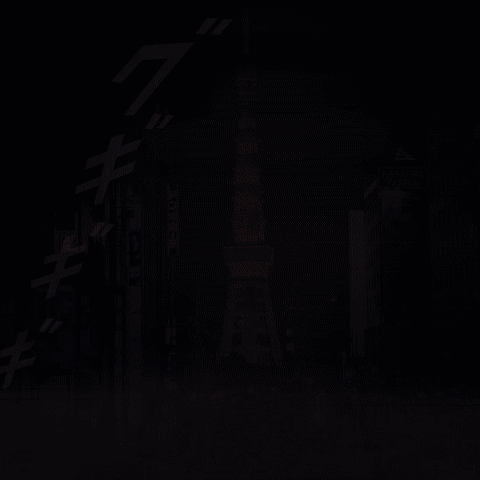
才蔵デカは部下のアロハを鋭い眼光で見つめながら話しかけた。
「アロハ。つまりは、どげなことや。おまえん推理、見立てば教えてくれ」
部下のアロハは涼風とアクアの言い争いの原因を声を潜めながら分析した。
「自分が思うに、あの二人、ブツの取り分のことで言い争ってんじゃないかと」
「ブツやと!ボラやなかとか?」
「あの二人は間違いなくシャブダチです」

アロハは強い眼差しを才蔵に向けた。その真剣な瞳を見つめてた才蔵はアロハに顔を近づけて低く囁いた。
「アロハ」
「なんですか」
「二度とそん手には乗らん」
強く握った拳でアロハの頭を強めにコツンとやった。
反対側の歩道では涼風とアクア九条の言い合いが続いている。だが道ゆく人たちは誰一人として、この二人に興味はなく地下鉄への急ぎ足だ。その雑踏の中で気配を消しながら情報集めに夢中になっているのはガッキーだった。二人の会話を聞き取ろうと必死だ。この内容をキャッチすることで明日からの楽屋での人気者が保証されるのだ。
情報屋ガッキーとして必死になるのは当然のことである。
弾む心を抑えながら会話を盗み聞いてたガッキーの顔色が、徐々に青ざめていった。なにやら、とんでもない情報を仕入れてしまったようだ。ガッキーは口の中で小さく…。
「ひゃく? ひゃくって…」
ガッキーは謎の言葉を呟いた。

道の往来で言い争いをしていた涼風とアクアの姿は見えなくなっていた。二人はそれぞれのタクシーに乗ってその場から消えたようだ。
二人がいなくなった道端のガードレールに、弱々しい姿でもたれかかってるガッキーに、横断歩道を渡ってきた才蔵とアロハが「どうしたのガッキー?」と心配そうに声をかけた。二人の顔を見たガッキーの瞳に、じんわりと涙が浮かんだ。
三人はカラオケボックスの中で顔を見合わせてる。
「ひゃくって、なんだよ?」。才蔵が不思議そうに聞いた。
「100で終わらせるって言ったんです…」
今にも泣き出しそうな声で、ガッキーは力なく答えた。
才蔵とアロハは、要領の得ないその言葉に「?」と顔を見合わせる。
「いやいや、さっぱり意味がわからないです。ガッキーさん、話が飛びすぎです。オレみたいなバカにも分かるように順を追って教えてください」
「オレにも、頼む」才蔵も懇願した。
「ごめんなさい、そうですよね…。オレ、あまりにもショックすぎて、ハイ説明をします」
ガッキーは才蔵とアロハに小さく頭を下げると、盗み聞きの中身を話しはじめた。
「あの二人、最初はチケットの話をしていたんですけど、そのうちに話がアッチコッチに飛び散らかして、お互いのプライベートの悪口になって、オレとしてはえぐい情報を仕入れたぞーと思ってたら、突然、涼風さんが『うるさいわねーそんな話はどーだっていいのよ、ホントはね、この話はさっきで終わりにするはずだったのよ』って言いだしたんです」
「終わらせる?」、才蔵が聞き返した。
「はい、八十八話で」
「なんすか、八十八話って?」
「八十八話というのは、涼風ママが三四郎さんとランランさんにBARでバイバイしたときのことです」
「・・・」
困惑顔の才蔵とアロハに、ガッキーは丁寧に説明をはじめた。
「これ、今、一気読みになっちゃったからトンチンカンに聞こえてると思いますけど、連載していたんです。そのときの話が八十八話だったんです。理解してもらえました?理解したと解釈して、次に進みますよ。そんで、あの路上で涼風さんがアクアさんに、こんなことを言ってたんです。VTRどーぞ」
ガッキーは、先ほどまでの落ちこみは何処にやら、収集した情報を得意満面に、似ていないモノマネを混ぜながら話をしている。
「耳くそほじくって、よーくお聞き」「失礼ね、あたし、耳くそなんてありません」「あるのよ、みんなあるの、なかったら妖怪よ」「ンまーあたしは妖怪じゃありません、レディなのよ!」
得意顔のガッキーの話は絶好調だ。かなりの脚色を入れながら才蔵とアロハをグングンと引きこませている。
「で、で、でー謎の数字の100。これだよね、これが気になるんだよね」
「そう、それが気になってんだよ」、才蔵が喰いつく。
「不思議だよね〜この数字。なんだと思〜う、へへ」
「そんなクイズ形式いらねえんだよ、早く教えろよ」
才蔵は語気を荒げた。
「ハイ、すみませんでした。100話で終わるということです」
「終わるって…この物語が終わるってことなんですか?」。
アロハが焦るように聞き返した。
「ハイ大当たりー」
嬉しそうに叫んだガッキーは、またまた調子にのって「その理由はどうしてなのでしょうかぁ〜」とクイズ形式の出題をした。
「理由があるのかよ」、才蔵が驚く。
「あれー?えー?」
素っ頓狂な声を出したアロハが「うそでしょう…その理由って、もしかして…」
「おおー。アロハのその顔、わかったのかなー」ガッキーはノリノリだ。
「なんだよ、アロハ教えろよ」才蔵は急かした。
「もしかして…」
「もしかして?」
「『100日後に死ぬワニ』の真似?」
アロハは、恐る恐るとガッキーの顔を窺い見た。
真顔のガッキーはニコリと微笑むと。
「ご名答ぉぉぉぉぉぉーハイ、それではその時の様子をどーぞ」と、はしゃいだ。
ガッキーの話に才蔵とアロハは息を飲んだ。
憔悴した二人の顔を楽しむようにガッキーは弾んでる。
「ばかだ…。そんな理由なの?」。才蔵は愕然となった。
「つか、ゾウじゃねえし、ワニだから。あのババア、IQ低っ…」。アロハは腐るように言葉を吐き出し、続けて「この大事な情報を浮かれて話すガッキーさんの頭もどうかしてるぞ」と睨んだ。
カラオケボックスの空間はガッキーの報告を終えてからの一時間ほどは、まるでお通夜のような時間となった。ガッキーと才蔵とアロハは溜息も底をついたのか押し黙ったまま、動くこともできない。ドリンクを下げにやってきた店員が、その静けさに「大丈夫ですか?」と声をかけたが三人には言葉を返すほどの気力は残っていない。
店員が出て行くと、ようやく口を開いたのは才蔵だった。
「振り返れば楽しかったよな」
「・・・」。ガッキーとアロハがチラリと才蔵を見た。
「涼風せいらのOKオケケ…楽しかったよ。涼風さんが辞めるというんだから、これは仕方ないんだよ」
神妙に話終えた才蔵にアロハが苛立った。
「は?なに大人ぶってんですか?本気でそう思ってんですか?俺は全然納得してないんですけど。こんなんで終わったらフラストレーション溜まりまくりですよ。こんな終わり方でいいんですか、あのシャブばばあーの戯言にハイそうですかって、今までご苦労様でしたって、誰が納得するんですか?誰もいないですよっ」
アロハの声は滲む悔しさでかすかに震えていた。
「うるせえよ、俺にあたるなよ」才蔵が言い返す。
「あたりますよ。才蔵さん、知ってますか?この物語、今日、何話目か知ってますか?」
「知らねえーよ、そんなのいちいち数えてられるかよ」
「いいですか、今日97話。つまり、残り四つです」
「四つ? 四個はだめの四つか…」
「うるせえよ、そんなボケいらねえんだよ」
「なんなんだよ、その言い方。俺は先輩だぞ」
「才蔵さんに聞きます」
アロハの瞳が強く鋭く才蔵を捉える。
「才蔵さんが今一番知りたいことはなんですか?」
「今、一番知りたいこと?」
「はい、そうです」
アロハは強く強く才蔵を見つめた。
今、一番知りたいことを教えろとアロハに問われた才蔵は悩んだ。なんだろ?なんと答えればアロハは納得するのだろうかと悩み、考えた。あ、なるほど…正解が見えたぞ。才蔵はアロハを見て、そして言った。
「アロハ。おまえって彼女いるの?」
「関係ねえよ、そんなこと、いねえよ、欲しいよ、すっげえー欲しいよ。だけど今の流れに全然関係ないからね。それが今一番知りたいことなの?バカじゃねえの、この物語に心残りはないんですかーつう話でしょうが!」
「あ…そういうことか」、才蔵は赤面した。
「あーガチで頭悪いなー才蔵デカはー。ガッキーさん、あなたはどうなんですか?最後に知っておきたいこと、ありますか?」
「あ…オレは…」
ガッキーは天井を見つめた。
知りたいことは山ほどあった。涼風さんの謎のチケットの女、その人との関係も知りたい。あと、尻に座薬を挿れるとき、どんな気持ちなのかも知りたい。そんで座薬を押しこむときって指も尻の中に突っこんじゃうのかも知りたいし、そのあとにウンコ臭くなった指をどれだけの勢いで洗うのかも知りたい。お…!びっくりしたぜ、俺の知りたいことって尻周りのことが多いじゃん、やべえよ、こんなことをアロハに言ったら本気で怒られるんだろうな〜と思った。
フト、アロハと目があった。怒り心頭、そんな目つきだ。
「今、真剣に考えてるから、もうちょっと待って」
「待てねえよ、どんだけ文字を使ってんだよ。ガッキーさんの言葉を待ってるだけで今日の分(98話)が終わっちゃったよー」
「ええっ!」。ガッキーと才蔵が叫んだ。
「残り二話だよ!」
「待って待って、待ってくれよ!」
その頃「やしろ荘」の住人たちも慌てていた。
「待って待って、俺と尚太郎の青春はこれからだよ」慎一が叫び、「いやいやいや、俺の努力のGo to パリコレを見て欲しいよ、そこ俺の人生の頂点なんだよー」浩輔が叫び、「つまらんぞーこがいな終わり方は!わしゃ来年大学を卒業する日に尚太郎に接吻するって決めとったんだ、それを見て欲しいんじゃー」、おっくんは泣き叫び、「僕はずーっとモノクロなんだぞ、カラーにしてよー」と北別府は便所の掃除道具を掲げて叫び、謎の住人の男は動揺を隠せない様子だ。「あの、俺、まだ名前すら名乗ってないんです、これから尚太郎との絡みも出てくるんじゃなかったの?嘘でしょ、このまま消えちゃうの?」。武雄は一升瓶を抱いて廃人のように眠っている。サチ子もよしえも叫んでる。「私のOL生活、不倫してのドロドロ話をするんじゃなかったのー」「私のバンドマンとしての涙、涙の話はしないのー」そして奈緒美も「オーイ、私の謎は?ちょいとーもしもーし」
兎にも角にもだ、昭和と令和の出演者たちは大慌てだ。
カラオケボックスの中でアロハに睨まれた蛙状態の才蔵とガッキーは「ンー最後に知りたいことかー」と唸っていた。
その二人を眺めていたアロハは大きな溜息を吐きながら「先輩たちって本気でバカなんですね。最後に知りたいことと言ったら一個しかないでしょうー三四郎さんですよ」と言った。

「三四郎?三四郎のなにを知りたいんだよ」
「あの人、謎だらけですよ。家にテレビがないんですよー仙人ですか?この舞台でオレは涼風婆さーんにものすごーく気をつかって生きてるのに三四郎さんはおだやかーに、上手に接してあの婆さんを立たせてて、あれは僧侶の域ですよ。普通ならストレスで胃が痛くなったり、酒を飲んで鬱憤を晴らしたりするけど、あの人酒を飲まないし、どうやって精神を保ってるのかを知りたくないですか?どんなプライベートか知りたくないですか?」
「なるほど、知りてえな、ウン知りたいよ」才蔵の瞳が輝きはじめる。
「え?アロハはその答えを持っていたのにオレたちに質問を投げかけてたの?」
「そりゃあそうですよ。段取りとしては『振り』は必要ですし。で、お二人が色々と考えて、最後にこの答えが出たときに『なるほどー』ってなったでしょう(笑)」
「おまえはオレたちのことをバカだ、バカだって言ってたけど、おまえの『振り』、文字使いすぎだからな、おまえがバカだよ」温厚なガッキーが怒鳴った。
「今は揉めてる場合じゃない。オレたちには時間も文字もないんだ。早速三四郎の身辺調査だ。オレは今、お父しゃんのDNAが疼いてる、張り込みに行くぞ」
「これからですか?つか三四郎さんがどこに住んでいるのか知ってるんですか?」アロハは慌てた。
「オイオイオイ、オレを誰だと思ってんだい?情報屋ガッキーだぜ」
善は急げと、その勢いで扉を開けた才蔵が「ヒッ」と息を飲み、扉を閉めたので「どうしたんですか?」とアロハが聞いた。
「三四郎がいた…」
「え?」
「便所から出てきて隣の部屋に入っていった」
「へえ〜三四郎さんカラオケとかに来るんだ、誰と一緒なのかな?早速プライベート一号だ」ガッキーは笑った。
三人は忍び足で部屋を出て、隣室扉の小さな窓から室内を覗き見た。テーブルにはコカコーラの空きグラスが置かれ、酒類のグラスは見えない。ソファーには三四郎の荷物だけが見えた。ひとり?なるほど…真面目な三四郎のことだから台詞の練習かラストに踊るダンスの練習をしているのだと三人は思った。だが三四郎の姿が見えないので、三人は首をグッと捻りながら扉の小さな窓から室内奥を見ると、大きな画面に向かってひとりカラオケをシャウトしてる三四郎がいた。シャウトシャウトの三四郎だ。ストレスを発散するかのようにブルーハーツを歌っている。
カラオケを出た三四郎は、次に二十四時間稼働ジムに行くと簡単なトレーニングで軽く汗をかき、サウナで疲れた体を休めると帰路に着いた。途中、コンビニで翌日の朝食用と思われる野菜サラダと豆乳を購入して、自宅マンションへと消えていった。
尾行トリオの才蔵、ガッキー、アロハの体力は限界に近かった。尾行によって何らかの成果が得られていたのなら心も弾むが、何ら変哲もない一人の男の後ろ姿を眺めてるだけの時間はゴールが見えない修行だった。特に才蔵は、昨日は朝方まで涼風との電話で寝不足である。
時計は夜中の三時を回った。三人は帰りたかった、だが、それを口にすることは許されない我慢比べのような雰囲気があり、誰かが(帰ろう)と言ってくれることをそれぞれが頭の中で願いながら、三四郎のマンション前の公園ベンチに座っていた。
「つまんないすね」
アロハがポツリと呟いた。
「オレが言いだしといて、なんですけど、三四郎さんのプライベートってクソですね。ジムで体を鍛えて、朝メシは野菜と豆乳、部屋に帰っても電気をつけないで…。そうやって忍者の末裔って役に徹したいのは分かりますけど、その一方でストレス抱えて、ひとりカラオケって…。つまんないよなーそんな人生」
アロハの言葉を聞きながら才蔵とガッキーは三四郎の部屋の窓を見上げた。そうなのだ、帰宅した三四郎の窓から明かりが漏れたのは玄関扉を開けたときに、共同通路からの灯りが一瞬射しこんだきりで、そのあとは暗いままなのだ。
「忍者ぶって瞑想してるか、ストレスから解放されてバタンって眠っているのかはわからないすけど、どっちにしてもつまらないプライベートですよ」
明るく、投げやり的な口調でそう言ったアロハを、ガッキーは驚きながら見つめた。
「アロハって明るく人の悪口を言うんだー?」
「ヘヘ、すみません、ハワイに憧れてるんで明るさが売りなんです、あ、このネタは秘密でお願いしますよ」
「バーカ。ガッキーが黙ってるわけないだろ」才蔵は笑った。
三四郎は、壁に身を隠すようにしながら窓の外の様子を窺い見ていた。
欠伸を噛み殺した才蔵が「あれ?」と呟いて二人を見た。
「なー続いてんじゃね?」
「なにがですか?」アロハが面倒くさそうに聞き返す。
「今、101話だぜ」
「え?」
「連載的には101話。違う?」
才蔵に問いかけられたアロハはスマホの中の小説ページを開き見ると、興奮しながら「ハイ、101話です、続いてます、続いてますよ」と答えた。
ガッキーと才蔵は、アロハのスマホを覗き見て「お?ホントだ」「続いてるよ、続いてるよー」と喜んだ。
三人は無邪気に喜びを分かち合いながら笑いはじめた。
三四郎は窓の下の公園で笑いあってる三人の男の姿を盗み見て、唇を噛むと、自室を見渡した。殺風景な部屋に、似つかわない4Kの85V型テレビが置いてある。テレビを見ない生活をしていたのに、先日衝動買いをしてしまったのだ。
その日は稽古オフ日で、ゆっくりと過ごすはずだったが、突然ストレスが体全身を襲い、買い物に走った結果、その勢いで購入してしまった代物だった。自宅に届いたときは後悔をした、なぜ、こんな不要なものを買ってしまったのだろう…。だが、それなのに、今、CSチャンネルの韓流ドラマにハマってしまっている。誰にも言えない秘密を二つも抱えてしまったのだ。
この日も、録画をしたドラマの続きが見たくて仕方がないのだが、マンション前の公園にあの三人がいる。テレビをつけると窓から漏れる光量でテレビの存在が知られてしまう…。
三四郎のストレスが膨らんできてる。
ジムを出てからの帰宅途中、誰かに後を尾けられてる気配を感じ、確かめようとコンビニに入り店内から外の様子を眺めたときは、愕然とした。尾行をしていたのは才蔵とアロハとガッキーだった。情報屋ガッキーにプライベートを暴かれるのか…そんな恐怖に襲われながら食べたくもない野菜と豆乳を買った。本当はチョコと甘い缶コーヒーが欲しかったが、ストイックな男として、この舞台の座長を任されてるイメージがある。
「くそ…」
三四郎は公園の三人を睨み見た。
「ドラマを見たいのに…続きが見たいのに…」
三四郎は悩んだ。そして結論を出した。
「消せるかな?」
そう呟くと、手で印を結びはじめた。それは忍者たちの護身法の九字切り、九字護身法のポーズである。これは人の邪心を祓ったり厄除けの効果もあるが、その場所を浄化する効果もある。
テレビがない生活のとき、忍者になりきろうと毎日様々な訓練をしていた三四郎は、時々その成果を試していたことがあった。そのひとつの忍法を今、やりはじめた。
三四郎が言った「消せるかな?」とは、どういう意味なのか…。相手の記憶を消すということである。過去に一度だけ成功したことがあった。二年前のことだ。食事の席で、つい共演者への愚痴をついてしまったとき(あ、しまった)と思い、話し相手に九字護身法と共に強い念を送りつづけたその結果、相手の男は「あれ?なんの話をしてたんだっけ?」となったことがあった。
三四郎は暗闇の部屋から窓の外の三人に向かって、強い念を頭と心に抱きながら唱えはじめる。
「臨・兵・闘・者・皆・陣・烈・在・前」
夜空は満月に輝いている。
九字護身法を三四郎が唱え終わったときだった…。
月夜が三人を照らし、スッと伸びてきた一筋の光が三人を包みこんだ。それは神秘的な光だった。光に包まれた才蔵、アロハ、ガッキーは、突然睡魔に襲われ、一人がガクンと寝落ちし、続いて二人三人と眠りに落ちていく。三人は不思議なくらいに体が軽くなり、幼き頃母親に抱かれていたときの安らぎを感じ、ポカポカ、ポカポカ、身体の芯から幸せを感じていった。
三四郎は慌てた。記憶を消すつもりが、強い念によって三人の存在を消してしまったのだ。
朝日に包まれながら公園で目を覚ました三人だったが、どれだけの時間が経過しようが…現実を受け止めることが出来ず、言葉を失い、その場から動けない。
その場所は眠ってしまった公園と思われるが、どこかが違う。周囲を見渡すと全ての風景が古いのだ。
それはそうだ。ここは昭和なのだ。
「どこなんですか、ここは…?」、才蔵が目の前の男たちに聞いた。
「誰なんですか、あなたたちは?」、ガッキーが目の前の男たちに聞いた。
「人形が喋りましたよね…」、アロハが目の前の人形に話しかけた。
脅える三人を見つめてるのは奥平、慎一、北別府、浩輔、謎の住人。そして尚太郎。
人形の尚太郎が話しかけたとき、才蔵とガッキーとアロハは腰が抜けるほどの恐怖と共に「人形が喋ったあー」「助けてー」「ここはどこだー」と叫んだ。
涼風は走っていた。
狂ったように叫びながら走ってる。
「冗談じゃないわよ、どーしてあいつら三人がこの物語の終わりになってるのよーこれはねー私の物語なのよ!『涼風せいらのOKオケケ』なのっ、わかってんのっ!私のお話で終わらせなさいよーこんなんで終わっていいわけないじゃないのさー中途半端にもほどがあるわよーっ」
涼風は誰に叫んでいるのか、とにかく走ってる。
「ムチャクチャじゃないのさー何で今と昭和がごちゃごちゃ
になってるのよー今の時代の話に戻しなさいよー」
そのとき、ドラマでよくありがちなシュチュエーションが起こった。車道を横切ろうとした涼風の目の前に激しいクラクションを鳴らしながら迫ってくる車が…。
涼風の頭の中にアクア九条に自慢をした「百日後に死ぬゾウ」の言葉がフラッシュバックした。
「死ぬの?私、ここで死ぬの?嘘でしょ、最悪な最終話じゃないのさ、いやだあぁぁぁー」
涼風の脳裏に走馬灯のように思い出が駆け巡った。
「お父さぁぁぁぁーん助けてぇぇー」
涼風は父親に助けを求めるように泣き叫んだ。あの日、十代の頃、忌み嫌った父親に、今、死を目の前にした、そのとき、涼風は助けを求めた。
猛スピードと思ってた車は安全運転すぎるほど安全運転をしていてゆっくりとスーッと停車をし、窓から顔を出したドライバーが「おばちゃん、危ないよ。横断歩道が青になったら歩くんだよ」と優しく注意をして走り去った。
安堵の息ついた涼風は天に向かって叫んだ。
「あたしの物語ぃぃぃぃ返してよぉぉぉぉ〜。ねえー素直になるからさー90話からやり直しをさせてよー。は?一気読みになったので90話がわからない?えーっとね、六本木の路上でアクア九条に悪態をついたあの時の話、え?覚えてない?ンまー読み返しなさいよ」
【おわり】