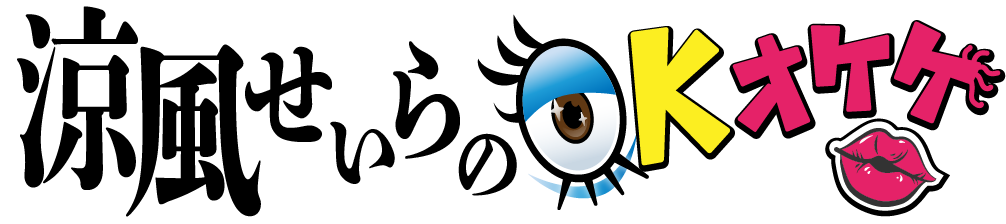10. 一枚のチケット
「伊賀の花嫁 その四 シングルベッド編」。二日目のソワレ公演は異常な盛りあがりをみせて、この日の幕を下ろした。

終演後の楽屋内も大いに盛りあがった。
気まずい気持ちのまま舞台にあがった才蔵だったが、共演者たちは何もなかったように自分との掛け合いを楽しんでくれたことで、このカンパニーの正式な一員になれたような気がした。
「なにごとも問題なく済んで良かったですね」
化粧前が隣席のアロハ・オギクボが笑いを堪えながら嬉しそうに話しかけてきた。
「俺、マジで尊敬しました。才蔵さんって勇気ある人だなーって」。
「オイ、アロハ。元を正せばおまえの適当な一言からはじまったんだからな、も〜勘弁してくれよ」
「へへ、今日、一杯おごりますんで、すみませんでした」
アロハ・オギクボが憎めない笑顔をみせたとき、二人の耳にアクア九条のキンキンとした甲高い声が聞こえてきた。
「ちょっと、あんた、いい加減にしなさいよ。そんなに持っているなら手放しなさいよ」
振り返ると楽屋の上座でアクア九条が涼風に詰め寄っている。オカダ三太はアクア九条を援護するように「そうだ、そうだ」と腕組みをしながら合いの手を入れていた。腕組みの右手には「博多通りもん」が握られていた。
「あんたのケチにもほどがあるわね、私の大切なお客さんがどうしても明後日の回を観たいって言ってるの、そこしか都合がつかないのよ、ね、持ってるんでしょう、その一枚譲りなさいよ」、アクア九条が再び叫んだ。
「だーめ、これは私のチケットなの、譲れませーん」
「ドケチ、キィー」
「うるさい、ウキィー」
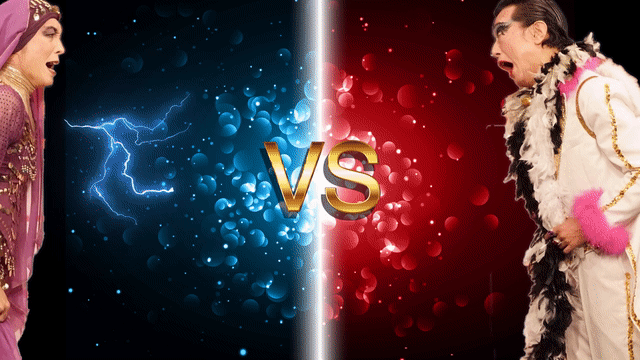
チケットのことで揉めていることは推測できた。
この舞台のチケットは完売したため出演者でも入手ができない状況になっており、役者たちはキャンセル待ちを条件に制作スタッフに「予約」を入れて虎の子の一枚をじっと待つという密かな争奪戦が行われているのだが、涼風がその虎の子チケットを何枚も持ってるという情報をキャッチしたアクアがその一枚を譲ってほしいと言ってるようだ。
才蔵とアロハ・オギクボがその様子を眺めていると、こそっとやってきたガッキーが事のあらましを小声で話しはじめた。
「なんでもね、さっきアクアさんがね、制作部屋に行って、チケット、なんとかならないのってお願いしたときに、とんでもない真実を知ってしまったんです」
「真実?」
才蔵とアロハ・オギクボが声を合わせて聞き返した。

ガッキーこと新垣実の最近の口癖は「このカンパニーに参加できて本当に勉強になる」だった。三十五才となった男は将来を真剣に考える年齢になってきたな、と思っていた矢先に今回の仕事に参加した。

芸能界に興味を抱いたのはレコード会社に勤めていた父親の影響だった。青年になったとき、臆することなくこの世界へと飛びこんだのだが、この二年間、全くの他人を演じることへの楽しみが薄れてきていた。いろいろな現場に呼ばれることは嬉しいことではあるが三十を過ぎたあたりから注意をしてくれる人が極端に減ったことで、自分自身が納得していない芝居に対しても「イイねー」と言われていることに不安を感じていたのだ。
だが、この現場では演出家から罵詈雑言を浴びせられ、周りの役者たちについていくことに精一杯の時間は懐かしい感覚であり、新鮮だった。なによりも自分より年上の役者たちが汗だくとなって踏ん張ってる姿に心を打たれた。
休憩時間になると稽古場の片隅でハアハアと息を整える毎日が続き、そのときに役者やスタッフたちの会話に耳を傾けることを覚えた。なにかを盗みたいという一心からの盗み見、盗み聞きをする癖がつき、気づけばカンパニー随一の情報屋となっていた。
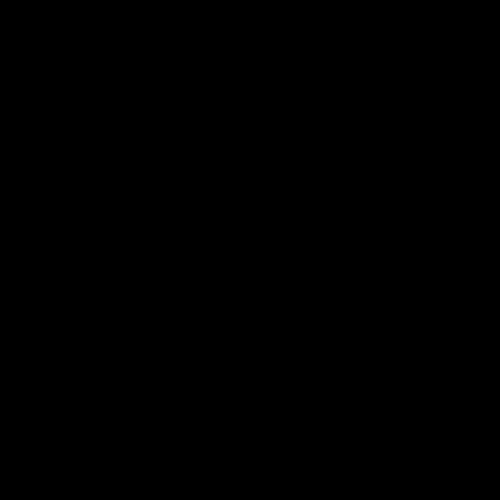
今日も終演後の楽屋で耳を澄ましていると、小声で会話をしていたアクア九条と涼風の言葉が聞こえてきたのだ。今夜の芝居の反省でも話し合ってるのだろうか…。メイクを落としながら耳をそばだてると、話の内容はチケットのことだとわかってきた。
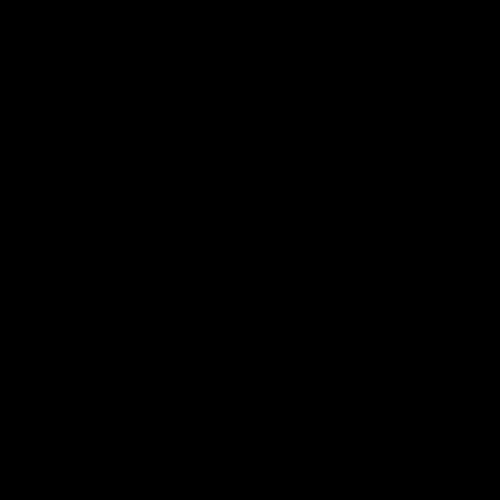
「なんでも、涼風さんはおんなじ人の名前で全公演分のチケットを一枚づづ確保しているらしいんだよ。で、で、で、ここからが問題で、その名前の人、今までの涼風さんの舞台にも、いっつも予約が入ってるんだけど一度も観にきたことがないらしいんだよ、ハイ、ガッキーからの特ダネでしたー」
「え?どういうことですか?」アロハは首を傾げた。
「そのへんの詳しいことはまったくわかんない。アクアさんが制作部屋で盗み聞きして、それを俺が今盗み聞きました、ハイ現場からは情報以上です、スタジオに返しまーす」
したり顔のガッキーは才蔵とアロハ・オギクボにウィンクをした。
ダンと机が叩かれた。
「いい加減にしてよ、ドケチ」
アクア九条は恨めしそうに吐き捨てると荷物をまとめて楽屋を出て行ってしまった。
オカダ三太がやんわりと涼風に話しかけた。
「涼風ちゃんさ、誰なのよ?その人?来るかこないかわからない人のチケットって…」
涼風は思い出していた。
あの日の奈緒美を。
彼女がいたから今の自分がいるのに…。
だが、恩人の奈緒美は今の涼風せいらの舞台を一度も観に来てくれていないのだ…。
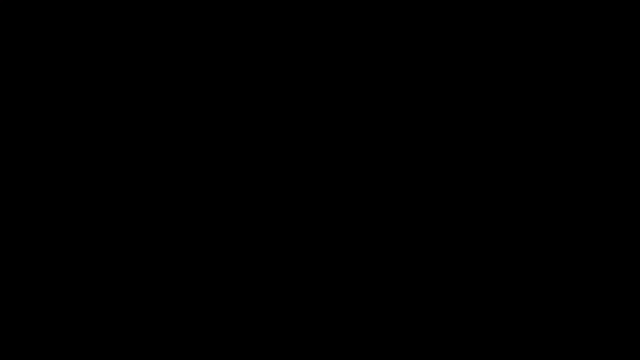
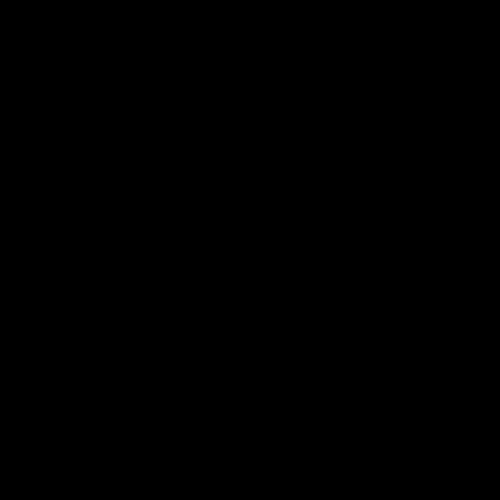
六本木の俳優座劇場は六本木通りに面している。
楽屋口から出てきたガッキーは賑やかな表通りを横目に指定された居酒屋へと急いだ。
店の扉を開けて店内を見渡すと、おーいココだココ、と手を振る戦友たちの姿が見える。「伊賀の花嫁」出演者の若手メンバーの下柘植栄次、韓国人のカン・ミンソンとイ・ジホ、そして綾部直之ことアーヤンが二杯目の中ジョッキを口につけた頃合いで口が柔らかくなっていた。

「遅すぎやで」「スミマセン、お先に食べてました、ここの唐揚げサイコーです」「筋肉喜んでます」「適当に頼んでいますけど追加があったらボクに言ってください、オーダーがダブルといけませんので」。待ち人たちは遅れてやってきたガッキーに矢継ぎ早に言葉をかけた。関西弁はアーヤン、礼儀正しい言葉づかいはミンソン、意味のないひと言を発したのは栄次、やたらと日本語が達者すぎるジホの四人はガッキーの到着を大歓迎している。
「ガッキーさん。生でいいですか?すみませーんお姉さーん、生ひとつ追加でお願いしまーす」、大きな声で注文をしたのはジホだった。よく喋る男でもあるが、とにかく気が利く男である。

若手と言われている彼らだが他所の現場に行けばそこそこのポジションを与えられ、もて囃される役者やアーティストだが、平均年齢の高い「伊賀の花嫁」のカンパニーでは若手扱いとされた。その立ち位置に不満があるかといえば全くそうではない、ガッキー同様にその突き放し感が逆に気持ちが良いらしい。「下手」「しかもクソ下手」「つまんない」「中学の演劇部に行って発声の勉強をしろ」「おまえは今日から役者と名乗るな、役者になりたいだけの役者と名乗れ」、演出家の言葉の棘が刺さりまくった一ヶ月間の稽古期間を共有した仲間たちは初日と本日二日目の観客の盛りあがりを肌で感じて、このカンパニーが「役者の再生工場」と言われてる所以を改めて知った。

稽古中、休憩時間にユジュンがこぼした言葉が印象的だった。
「軍隊の教官より怖いです…」

戦友となった若手たちは今夜の涼風とアクア九条の一件に頭を悩ましていた。終演後の楽屋での出来事はその場にいた者たちを気まずい空気にさせたが、そのことを楽屋で口にする者はいなかった。みな、黙々と帰る準備をはじめ、なにごともなかったかのように「お疲れさまでした、明日もよろしくお願いします」、と楽屋を出た。
だが、それぞれが心の奥でモヤついていた。そのとき栄次から個々にLINEが入り、集合と相成った。座組みの中で最年少の男だが仲間思いの口下手で熱い男である。熱い男は三人を集めたが、その場を仕切るほどの話術を持ち合わせてなく、沈黙の時間が続き、それでも彼らには現状の問題が共有されていたので、まずは飲もうかとなった。
そのうちに誰とはなしはじまった今夜の一件に対して、話の方向が涼風とアクア九条のどちらについたらいいんだ、となり、そこに答えを出せるわけではなく、では自分たちで解決できることはしていこうとなり、そこで新鮮な情報を求めて情報屋のガッキーを呼び出した。
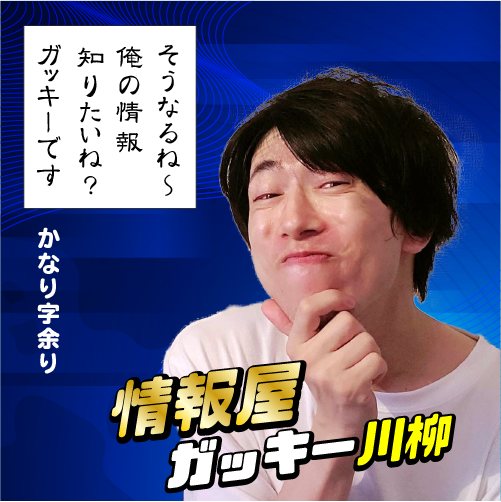
「ごめんよ、ごめんなさいね、失礼しますよ〜」と手刀を切りながらアーヤンの隣に座ったガッキーは、丁度運ばれてきた生ビールのジョッキを持ち上げると、「まずは本日二日目にお疲れさまでしたー」と音頭をとりグイッと喉に流しこんだ。
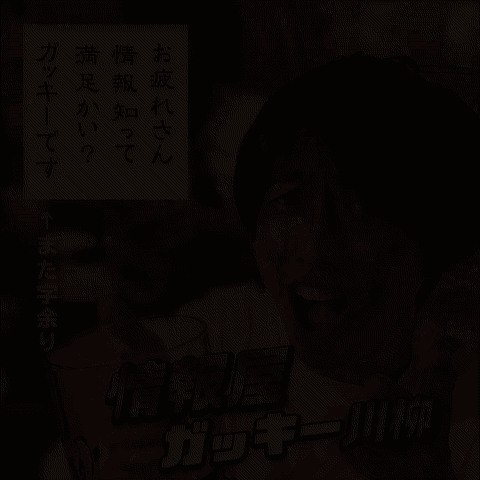
だが、得意げに話をはじめたガッキーの話には楽屋で漏れ聞こえていた以上の新情報は含まれていなかったので戦友たちは心のどこかで(つまんねえ…)と思っていたが、同じくくりの若手といってもガッキーは年上なので、それも言葉にできず、ミンソンは欠伸を噛み殺すのに必死だった。
「ガッキー。もうええわ、話がつまらへんし」
「え?」、とガッキーはアーヤンの顔を見た。
「その話、涼風さんが全部のステージにおんなじ名前の人で予約を入れてたちゅう話、みんな知ってんで。期待しとったのはそんな話ちゃうし、もうええよ、みんな飽きとるし」
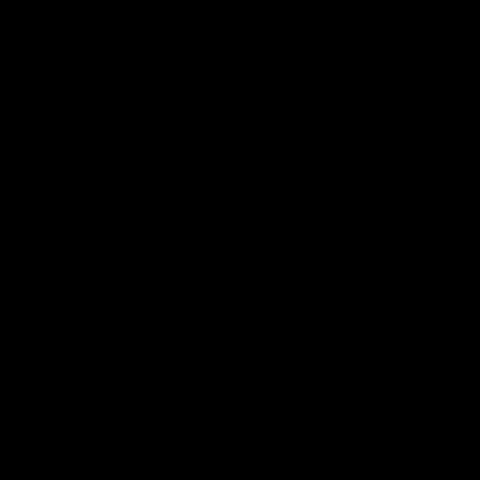
兵庫県伊丹市で生まれ育ったアーヤンの夢は自衛隊員となって日本国民を助けるヒーローになることだった。彼が六歳の誕生日を迎えようとしていた三日前に伊丹の街はグラリと揺れた。一九九五年一月十七日、阪神淡路大震災だ。その日からは恐怖の毎日だった。だが、その恐怖心を救ってくれたのは伊丹市内に駐屯している陸上自衛隊第三師団の自衛隊員たちの姿であった。
そのとき少年はヒーロを知ったのだ。73式大型、中型のトラックに乗りこみ救助活動へと向かう自衛隊の姿を近所の同級生たちと見つめながら、僕もいつか…と瞳を輝かせた。その気持ちは中学生、高校生になっても変わることはなく強い男への憧れは日に日に強くなった。気がつくといつの間にか目尻がクイッと上がり鋭い眼光となり、ソプラノの美声少年は声変わりのときにドスの効いたハスキーボイスマンとなっていた。
高校生のある日、友人の家でヒーロードラマを見ていると友人の兄が、これ無茶苦茶におもろいねんとビデオデッキにVHSテープを挿しこみ無理矢理に東映Vシネマの極道モノドラマを見せた。なぜか、アーヤンは完全にハマった。そこに新たなヒーロー像を見つけてしまい、役者への道を歩きはじめたいと思った。そのことを母親に告げると「あんたは地元のヒーローになるんやなかったん?極道になるために今日まで生きてきたの、おかあちゃんは悲しいで、悲しすぎるわぁ」と大泣きされた。
上京と同時に俳優への道を目指したアーヤンだったが、極道モノのオーディションはことごとく落ちた。見た目と違い繊細、且つ心優しき男はキラキラ系の舞台が主戦場となり、ガッキーとはそれらの舞台で共演をした周知の仲だったのでミンソンたちの心の声の代弁者として「話がつまらへん」、と言葉を挟んだ。
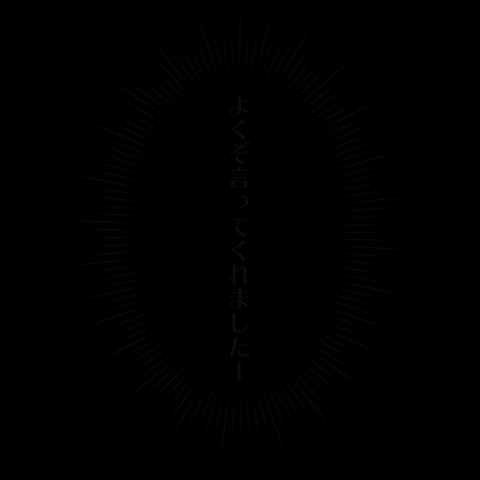
アーヤンのひと言でガッキーは、ごめん、と呟きシュンとした。店に入ってきたときの輝きは完全に失せていた。
それからの一時間ほどの会話はたいした盛りあがりもなく、話題は軍隊経験をしたミンソンの話へと移り、おおー凄いなーとなり、ジホはいつ行くの?そんな細い体で大丈夫なん?鉄砲とか持って走れるの?筋肉は大事だよ。泣いちゃうんじゃないのーなどと、いじられていたジホだったが口を真一文字にして「ボクだってガンバリますよ、国のために」、と言ったひと言に、そうだよな、考えれば韓国って休戦中なんだよな、「つまりは戦争中なんだよね」、と多少のかじりついた程度の知識を引っ張りだしながらアーヤンと栄次は徴兵制度の韓国はすごいなーと結んだ。

さあそろそろ散会だとなり、ジホが勘定伝票を見ながら携帯の電卓で割り勘料金を叩き出したときに、ガッキーが「ごめんね」と呟いた。
ン?となった一同が彼を見るとガッキーは申し訳ない顔をしながら、「たいした情報もないのに、みんなに期待させちゃったみたいで本当にごめん」、と頭を下げた。
「もうええよ、そのことは」。アーヤンが笑った。
「涼風さんが押さえてるチケットの人の名前、女の人としかわからなくて…こんな程度の情報で調子にのってた自分が恥ずかしいよ」
「…」。全員がガッキーを見つめた。
見つめられたガッキーは「え?なに?」、と動揺した。
「女?」「涼風さんにオンナ?」「え、あの人にそういう相手がいたってこと?」「筋肉うずくんだけどー」、凄まじい質問が飛び交うなか、ミンソンが手をあげた。
「ハイ。あと一時間くらい、飲みませんか?」

その頃、六本木の小さなバーで涼風はランランと三四郎とグラスを傾けていた。

「涼風さん、誰なんですか、その奈緒美さんという人?」、とランランが聞いた。
「その人とはどういう関係だったんですか?」
三四郎が涼風の顔を窺いながら尋ねた。
涼風はあの頃を思い出すようにグラスを見つめ、そして優しく呟いた。
「奈緒美さん…。私のとっても大切な人なの…」