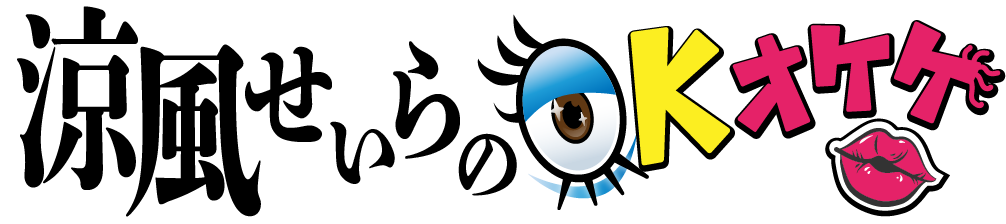大衆居酒屋はサラリーマンと学生たちで賑わっていた。
店内の片隅の席でコップに瓶ビールを注いでもらいながら尚太郎は思い出していた。
高校一年の夏休み、友人とキャンプに行ったときに悪ぶって酒を飲んだのだが1分もしないうちに顔がうわあ〜と真っ赤になったと思ったら、次に身体中が熱くなり、着ていた洋服を全部脱いでしまったのだ。後日、そのときのことを考えた。
酒は毒だ。
普段は黙々と職人をしてる父親が酒を飲むと気が大きくなり、家族に手をあげるのはあの液体が原因なのだ。自分には父親の血が流れている、この味を覚えることは毒だ。

だから俺は永遠にお酒は飲まないと決めたのに、今、グラスにビールを注がれている…。
そしてゆっくりと伸びてきた奥平の手が尚太郎の拳を触った。
尚太郎はヒッと奥平を見た。
奥平は尚太郎をじーっと見つめ、ニタリと唇を舐めた。

あゝこの人はやはりそうだったんだ…尚太郎は確信をした。
あのときの頬のキスは寝ぼけていたんじゃなく本気だったんだ。
助けてください、誰か助けてください。
そう願っても声が出なかった。
「オレが怖いんじゃろ?」
顔をあげてテーブルの向かい側の奥平を見ると、奥平は泣き出しそうな尚太郎の顔を見てケタケタと笑い出した。
奥平は、突然無口になったこと、強面の男や、男をスキな男になりすましたこと、これらの行動の全てが武雄の部屋を出てからのゲームだと教えた。
からくりが分かった尚太郎は「本気で泣きそうだったんですからねー」と泣きそうな気持ちを抑えながら笑顔を見せたが、奥平は話しをつづけた。
「尚太郎。キミが本気で家出をするというのなら独りで生きていくということなんじゃ。この世の中にゃあいろいろな奴がおる。悪い奴も多い、だけどそがいな野郎から守ってくれる親はおらんということじゃ。われは親を捨てたんじゃ、家出をするというこたぁそがいなことなんじゃぞ、その覚悟はできとるのか? わしゃそのことを聞きたいんじゃ」
「われは凄いな、家を捨てるんじゃぞ、普通はできんぜ」
この夜、大衆居酒屋で奥平が言った言葉が脳裏から離れなかった。

令和2年5月25日