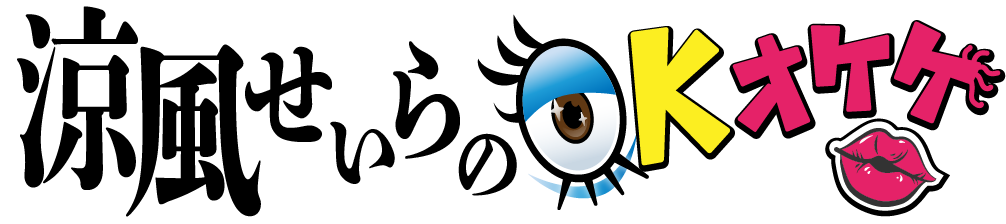「レンチを床におけ」。
小太りの男が低く唸った。
「・・・」
「知らねえぞ、どうなっても、ケンカふっかけてきたのはおめえだ、おけよ、コノヤロ」。ひょろ長が笑った。
「お金を返してください」
尚太郎は泣きそうな声で懇願した。
「僕のお給料です、お願いします、返してください」
床に膝をつき頭を下げてお願いをした。なぜだ、どうして金を奪った連中に俺は頭を下げているんだ…道理が合わない、だが、これしか思いつかなかったのだ。こいつらには喧嘩では勝てない、勝てるわけがない、それならば情に訴えるしかない、お願いをするしかないのだ。
小太りの男がゆっくりと腰を落とすと尚太郎に優しく囁いた。
「だったら警察に行けよ、ボク、お金を取られました、家出してきたボクのお金を取られましたってよ、ケケケ」
尚太郎は笑い合う二人の顔を見た。

知っているんだ…自分の過去を。
「オイ、家出少年、警察には秘密にしてやるから二度と俺らの前に現れんな」。
男たちは腹を抱えて笑い、小太りが「慰謝料だ」と尚太郎の口に千円札を突っこむとタオルを拾いあげて出て行った。

何も言い返せなかった。
何もできなかった。
家を捨て、親を捨てて生きるということの現実を知った。
悔しくて悔しくて喉の奥で静かに泣くことしかできなかった。
この日は長野県上田にある尚太郎が通っていた高校の卒業式だった。

尚太郎が卒業生扱いとして卒業アルバムに参加できたのは父、吉次が学校に何度も頭を下げて退校処分を免れたおかげだった。
このことを尚太郎が知るのは五年後である。
令和2年5月31日