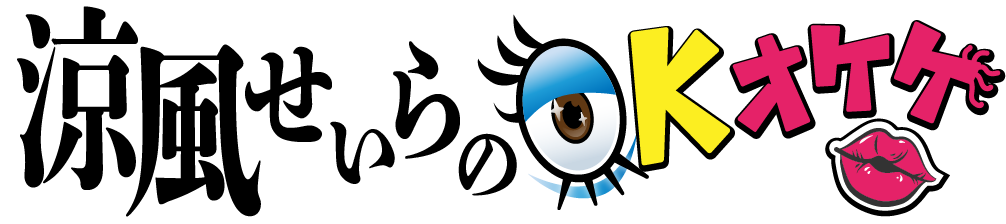それ以降、サチ子とよしえがちょくちょくと遊びに来るようになったのは、彼女たちの目的が浩輔と慎一だとわかった。
そのときぐらいから、尚太郎の心はグラリと病みはじめた。食事の中盤からの話題はいつも浩輔と慎一の大学での話となり、その会話に社会人となったサチ子とよしえが「あーわかるー」「あるある、そういうことー」「私のときはねー」と参加して、そして、その過去話にみんなが笑った。

尚太郎は孤独になっていた。
その会話に入っていけないのだ。
恥ずかしかった。
慎一に連れられて歩いた大学の体験しかしていない自分が恥ずかしく仕方がないのだ。ここにいるみんなは、あのキラキラとしたキャンパスのグリーンパークに腰を落として仲間たちとワイワイガヤガヤと騒いでいると想像するだけで辛くなった。
終盤は決まって努力の男の慎一と無駄に明るい浩輔が話題の中心となり、この日はマイケル・ジャクソンに憧れてる慎一が覚えたてのムーンウォークをお披露目し、浩輔はつぶらな瞳にグイッと力を入れながら格好つけたモデルの歩き方を見せ、サチ子とよしえと奥平は黄色い歓声を送った。

尚太郎の冷めた心と目は、この場にいることを強く拒んでいたが、その気持ちを理解する人間はいなかった。愛想笑いをしながら辛い辛い時間だけが過ぎていた。

令和2年7月7日