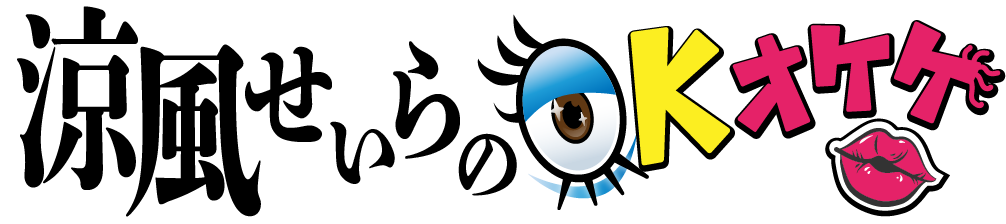3.夢追い人たちとの遭遇編
引き戸を開けると三十センチかける一メートル五十センチ程度の小さな板場と四畳半の畳の部屋。一間の押し入れと天袋。畳には万年床の煎餅布団と簡易的なちゃぶ台。窓は西向き。壁には本棚と文机が並び、大学の授業で使う教科書と共に何冊かの平凡パンチが置かれ、そして松田聖子と甲斐智枝美の大きなポスターが最高の笑顔でこちらを見つめていた。
そこが武雄の東京人としての住処だった。

「びっくりしたぜー突然なんだもんよーハハハ。よし、東京を案内してやる、どこに行きたい? どこにでも連れてってやるぜぇぇ」。寝起きの武雄は東京弁で尚太郎の訪問を大変喜んでくれたが片膝を立てたガラパンと太ももの隙間からポロンとチンチンが出ていたのは残念だった。

東京で初めて迎える夜は刺激的でエネルギッシュな時間そのものとなった。
どこにでも連れてってやると豪語した武雄だったが仕送りとバイト代と奨学金を使い果たしていたので高円寺散歩とり、この街に点在する幾つものライブハウスの前を通るたびに、この店はこういう系統のバンドが多く出演してて〜店内は入り口にバーカウンターがあって、そこでドリンクを頼み〜好きな席に座って〜と細かく説明するのだが決して店内に入ることはない。それでも尚太郎には十分すぎる貴重な東京見物だ。
夜は武雄の部屋で尚太郎の歓迎会となり、午前中に遭遇したアパートの住人の下着とTシャツの女と奈緒美も参加してくれた。当然普段着で。

もう一人、武雄の大学の友人の奥平徹に囲まれながらワイワイとやった。下着の女の恋窪サチ子は奈緒美と同じ美大に通う三年生で将来は出版に関係するアートデザイナーを志している。パジャマの片倉よしえはプロのミュージシャンを夢見てバンド活動をする二十歳だと知った。
奥平の実家は百年も続く広島の酒造所で卒業後は実家に帰るので「大学での四年間はトコトン遊ぶんじゃ」と豪語するお坊ちゃんだ。武雄たちから「おっくん」と呼ばれている奥平は、そう言うと豪快に笑ってみせた。
みんながそれぞれの夢を持っていた。
尚太郎は同年代の彼らの夢の話に心が弾む時間を過ごした。

翌朝。尚太郎は寝苦しくて目が覚めた。
ひと組の煎餅布団に尚太郎と武雄と奥平で寝たのだが、隣で眠ってる奥平の左足が尚太郎の腰に覆いかぶさっていたのだ。
尚太郎は奥平を起こさないように奥平の足を静かに持ち上げて自分の体から離したとき、奥平が「ンン…」とかすかに目を開けて「ごめんな…ありがとのぅ」と言って尚太郎の頬にチュッとキスをした。
え? なになに? なんなの?

奥平を見ると、奥平は鼾をかいて眠っていた。

武雄と奥平は朝十時になっても起きてくる様子ははなかった。大学生の生活ってそんなものだよ、と洗面所で顔を洗ってる奈緒美が尚太郎に笑いながら教えた。大学に入るまではみんな必死だったんだけど入っちゃうとあんなのばっかりだもん。


「奈緒美さんもですか?」
「うん、似たようなもんかな、フフ」
「奈緒美さんの夢ってなんですか?」
「あ、それ聞いちゃう?」
「ハイ、聞きたいです」
「柴田恭兵の彼女になること」。奈緒美は嬉しそうに、そう言うと
「覚えてる? 原宿の舞台? 恭平、あのときの主役の人。私、あの人とつき合えるなら奴隷でもいいの。だからね、恭兵に近づくために今年の授業から舞台美術の勉強をはじめるんだ」
奴隷という言葉は、とてつもなく淫靡で尚太郎の心の底でありとあらゆるスケベを想像させたが、その気持ちを無理矢理に抑えて、
「舞台美術ってなんですか?」と訊ねた。
「簡単にいうと舞台の設計図かな」
奈緒美は瞳を輝かせながら、そこから一時間ほど話をしたが尚太郎にはチンプンカンプンだ。だが小さな町にいたら知らなかった世界の話に、やはり心が躍り、俺も東京で夢を語りたいなーと、はやる気持ちを抑えるのに必死だった。

その日の夜、昨夜のメンバーがなけなしの金を出しあって尚太郎のためにスキヤキ鍋を振る舞ったときのことだった。

武雄が素っ頓狂な声をあげた。
「え? 家出? 尚太郎、家出をしてきたの?」
「はい」と尚太郎。
「あるある、そういう時期」、面白そうに相槌を打ったのはバンドマンのよしえで、「で、予定は一週間くらい?」と聞いた。
「いえ…。ずっとです」
「ずっとって…ずーっとということ? 本気の家出ってことなの?」。サチ子の声が上擦る。
「はい。俺も東京で夢をつかまえたいんです」
「待て待て」。焦ったのは武雄だった。「そのこと、おじさんは知ってるのか?」

尚太郎はかぶりを振ると「黙って出てきました」と伝え、
そして武雄に向かって正座をすると頭を下げた。
「武雄さん、ここに住まさせてください」
「ムリだよ」、武雄は食い気味に答えた。
「俺、イヤだよ、あのおじさんに目をつけられるのは…そんなことを知られたら俺が上田に帰れなくなっちゃうって、ムリムリムリムリムリ」
脅える武雄の姿にサチ子が聞いた。
「尚太郎くんのお父さんって怖い人なの?」
「ああ、星一徹も降参する」

そのひと言に皆の顔が強張り、武雄は怒鳴った。
「尚太郎、帰ってくれ」

「家出をした尚太郎を俺が匿うなんて絶対にムリだ」
武雄の言葉に尚太郎の頭の中はこんがらがった。武雄先輩だけが頼りだったのに、この人に見捨てられたら行き場所はなくなるわけで、俺はどうなってしまうんだ…美味しかったスキヤキは喉を通らなくなっていた。

東京での一泊二日で改めて感じたことは、この街には夢と自由が溢れていて、その一人になりたかった…。だけどこのままでは上田に帰るしかないのか、弱気な気持ちが心を支配しはじめた、そのとき奈緒美が笑顔を向けた。
「じゃあさ、私の部屋に住む?」
「え?」、尚太郎は奈緒美を見た。
「あ〜それいいアイデアじゃん。それだったら武雄くんが匿ってることにはならないんだし、尚太郎くん、奈緒美の部屋に飽きたら私のところでもいいよ」、とサチ子が賛同すると、よしえが「だったらさー私たちの部屋を行ったり来たりする? 楽しそー」と言った。
尚太郎は女の子の部屋に居候できる自分の人生を想像した。


「いやいや、それじゃと意味がないじゃろ」
奥平が口を挟んだ。
「考えてみぃや。仮に尚太郎の父ちゃんが息子は奈緒美さんちゅう女の部屋に居るとわかったとしよう。そんとき、どう思う?そのアパートにゃあ武雄もおるのか?なるほどなーこのエゲツない青写真を描いたんは武雄というわけか、キッチリとケジメをつけるしかないのお」。
奥平は地元広島への格別な愛の印として東京に来ても東京弁には流されないという鉄則を持ち続け、日常会話でも常に広島弁を使っていた。普段は愛嬌のある和んだ方言なのだが、ここ一番のときには「仁義なき戦い」の菅原文太口調になる癖があった。
「よしてくれよ」、武雄は泣きそうだった。
「つまりじゃ、奈緒美さんたちの善意は武雄をおとしめる怖さを秘めとるちゅうわけじゃ。尚太郎、われはそうまでして恩人である武雄を困らせたいのか」
「いえ…」。この言葉で尚太郎のパラダイス計画の夢は儚く消えた。
「そこでの、わしゃ考えたんじゃ」
全員が奥平を見つめた。
「わしのアパートなら安全じゃろ」
その言葉に武雄も奈緒美たちも、なるほどーと声をあげて喜んだが尚太郎は朝のキスを思い出した。
あれはなんだったんだろ…。
この人と二人で暮らすのはとっても怖い…と思った。